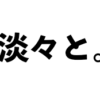アウトプットの「質」を上げるには、まずインプットの「量」を上げる
僕は今、いろんな形でアウトプットをしています。
こうしてブログを綴ることもそう。
人に会って、話をすることもそう。
人前で話す機会をいただくこともそうです。
こうしてアウトプットをしている人は、あることに気づくと思います。
それは、”アウトプットなんて、あっという間につきる”ということ。
よく「アウトプットをしたい」「アウトプットする場が欲しい」という声を耳にします。
大学という閉ざされた空間にいると、余計にそのように感じられるのかもしれません。
僕だって、そう思っていました。ずっと。
だけども、一方でそれでもインプットし続けていて良かったなと思うことがありました。それは実際に自分がアウトプットするようになってから。
アウトプットなんて、簡単につきます。
例えば、人前で何かを話すという経験をしたとします。
数ヶ月、場合によっては数回、人の前で話をすると、もう話すことなんでなくなってしまいます。
という経験は、例えば学生活動を少しでもされた方なら分かると思います。
ブログだってそうです。
日々の日記を綴るのならば、毎日の中のちょっとした気づきを綴ればいい。
でも、それだって自分自身が思考のアンテナを張っていないと、すぐに書けなくなってしまいます。
ましてや、何かを発信するためにブログを書いておられるならば、発信することなんてすぐになくなってしまいます。
これは10代の頃の僕が、何か発信をするために書いていた経験から分かります。
ほんとに。
その頃の僕は、何かアウトプットをしたいという欲求から、ブログを書こう!と思い立ったのもつかの間。
ひと月もしないうちに、何を書けばいいか分からなくなってしまう…
という苦い経験を何度もしています。
アウトプットの「質」を上げるには、インプットの「量」を上げる
まず、膨大な量のインプットをすること。
全てはそこから始まると思います。
特に何か発信をしたい人は、インプットし続けないと、あっという間につまらないアウトプットしかできなくなります。
アウトプットの質を上げるには、アウトプット自体の量も上げる必要があります。
しかしそもそもの前提として、インプットの量を上げなければ、スタートラインにすら立てない。
僕はそう思っています。
アウトプットというのは、インプットし続けた延長線上にあるものです。
イメージとしては、「コップ」に水を注ぐこと。
コップに水を注ぐことをイメージしてください。
少しずつ、少しずつ水を溜めていきます。
でも、コップの中に水が入っているかどうかは、外から見ると分からない。
でも確実に少しずつ、水は溜まっていきます。
これが人の「成長」なんだと思います。
成長は、時には外から見ては分からない。
分かるのは、コップに水が満杯になって、溢れ出たときです。
それが自然なアウトプットなんですね。
もうお分かりになると思いますが、コップに水を溜めることをしなければ、あっという間にコップは空になってしまうんですね。
だからこそ、日々の瞬間瞬間で徹底的に思考し、本を読み、人に会い、あらゆることに気づいていくんです。
それがコップに水を溜めること。
水を溜める器を大きくしよう
と、上の話までは、僕が大学に入るときに思っていたこと。
徹底的にインプットし続けよう。
そうすれば、いつか必ず溢れ出す瞬間がくるだろうと。
でも今になって思うことは、必ずしも早く溢れ出すことがいいとは限らないかもな…
ということです。
コップというのは、言うなれば自分自身の器です。
その器は、大きければ大きいほどいい。
それが後に、自分の人間としての器になるから。
だからこそ、「結果がでる=溢れ出す」ということは、そんなに早く経験しなくてもいいと思っています。
力を溜める。
あらゆるものに挑戦し、失敗し、それらを飲み込むほどに自分の器は大きくなっていきます。
そうすれば、いずれ必ず溢れ出す瞬間がくるんですね。
それを焦る必要は、全くない。
僕の20代の位置付けは、迷路を塗りつぶす時期です。
あらゆることを、飲み込む。
飲み込むというのは、最初から否定せずに、1回は自分の中に入れてみるということ。
「これは自分がすることじゃない」
と最初から否定の立場論を取ると、そこから先に成長はないんですね。
それは本当にものすごくもったいない。
1回は自分に入れてみる。
それで合わなかったのならば、そこで初めて別の選択をすればいいんです。
僕はそう思います。
やってみる。
それでこれは自分がやるべきではないと感じたならば、そこで”やらない”という選択をすればいい。
自分の限界に蓋をしないことです。
限界に挑戦することでしか、人の成長はないからです。
自分の枠は、自分で決めない。
僕らの持つ可能性は、ほんとに無限大なんですから。
ここまで読んでくれて、ありがとう。
<追伸>
「もっともっと、枠の広い人に会いなさい」
と教え続けてくれたあなたに、感謝です。
これからは、同じ社会人として、共に切磋していきますね。